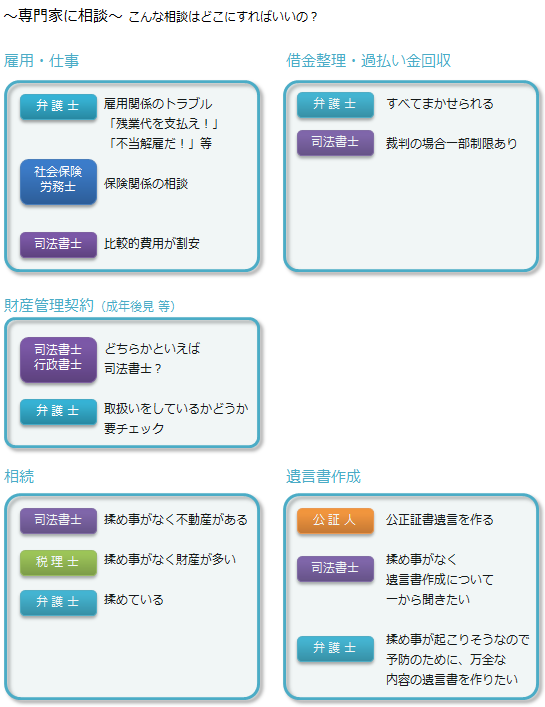リゾート会員権(岡本ホテル詐欺)事件
水曜日, 2月 9th, 2011
「岡本ホテル グループ元オーナーら逮捕 組織的詐欺容疑」
岡本ホテルというリゾート会員権が、
そもそも詐欺だったのではないかとの疑いで、警察の捜査がすすんでいます。
岡本ホテルは、少し前まで色々なところで広告が出ていたような気がします。
平成20年には、岡本ホテル同様大々的に広告を打っていた、
リゾート会員権のパルアクティブ株式会社も
民事再生という倒産手続をとっています。
私も以前、東急ハーヴェストというリゾート会員権を持っていた時期がありました。
その頃東急ハーヴェストは、
毎年結構な金額の維持費がかかるし、毎回の利用料も必ずしも安くないのに対して、
岡本ホテルやパルアクティブのように広告でよく見かける施設には
無料宿泊券があったりして随分安くて、すごいなあと思っていました。
しかし、東急から報告される積立金の使途(今回は、○○を取り替えました等)をみたり、
物件全体の維持コスト、従業員の給料等を考えると、
東急ハーヴェストの金額が不当とも思えませんでした。
当時は「安いところは、きっとろくでもない食事が出たり、
掃除が行き届いていなかったりするに違いない」なんて考えていました。
しかし実際は、食事や掃除云々の問題ではなく
それどころか、そもそも成り立たなくて倒産してしまったり、
詐欺だったりというわけで、なかなか大変です。
特別な権利を持っている人は、
普通の人が持っていない得な思いができるに違いないという潜在意識に働きかけるので、
びっくりする程お得で、
普通ならどこかおかしいのではと疑うような事でも
不信感が生まれないのかも知れません。
本当は、車や不動産と同じで、会員権も
持っていればお得どころか、それに伴う経済的な負担はそれなりに大きいのです。
さて、リゾート会員権については、法的性質については色々な種類のものがあります。
会員権については、主にゴルフ会員権を中心に法律論の議論が進んでいます。
ただ、リゾート会員権には、区分所有権があるもの(”所有型”と言われたりします)
も多くあります(私が所有していたものもそうでした)。
ホテルをマンションのように、区分所有権の対象にして、
その区分所有権を会員で共有するというものです。
この形式は、ゴルフ会員権ではあまりなく、リゾート会員権特有のものだろうと思います。
このようなリゾート会員権の区分所有権に、
区分所有法(いわゆるマンション法)をそのまま適用してよいのかというと、
何となく違和感があり、法的な問題としては興味があります。
でも、俗世から離れるためのリゾート会員権ですから、
法律的なトラブルとは無縁であって欲しいものです。
岡本ホテルというリゾート会員権が、
そもそも詐欺だったのではないかとの疑いで、警察の捜査がすすんでいます。
岡本ホテルは、少し前まで色々なところで広告が出ていたような気がします。
平成20年には、岡本ホテル同様大々的に広告を打っていた、
リゾート会員権のパルアクティブ株式会社も
民事再生という倒産手続をとっています。
私も以前、東急ハーヴェストというリゾート会員権を持っていた時期がありました。
その頃東急ハーヴェストは、
毎年結構な金額の維持費がかかるし、毎回の利用料も必ずしも安くないのに対して、
岡本ホテルやパルアクティブのように広告でよく見かける施設には
無料宿泊券があったりして随分安くて、すごいなあと思っていました。
しかし、東急から報告される積立金の使途(今回は、○○を取り替えました等)をみたり、
物件全体の維持コスト、従業員の給料等を考えると、
東急ハーヴェストの金額が不当とも思えませんでした。
当時は「安いところは、きっとろくでもない食事が出たり、
掃除が行き届いていなかったりするに違いない」なんて考えていました。
しかし実際は、食事や掃除云々の問題ではなく
それどころか、そもそも成り立たなくて倒産してしまったり、
詐欺だったりというわけで、なかなか大変です。
特別な権利を持っている人は、
普通の人が持っていない得な思いができるに違いないという潜在意識に働きかけるので、
びっくりする程お得で、
普通ならどこかおかしいのではと疑うような事でも
不信感が生まれないのかも知れません。
本当は、車や不動産と同じで、会員権も
持っていればお得どころか、それに伴う経済的な負担はそれなりに大きいのです。
さて、リゾート会員権については、法的性質については色々な種類のものがあります。
会員権については、主にゴルフ会員権を中心に法律論の議論が進んでいます。
ただ、リゾート会員権には、区分所有権があるもの(”所有型”と言われたりします)
も多くあります(私が所有していたものもそうでした)。
ホテルをマンションのように、区分所有権の対象にして、
その区分所有権を会員で共有するというものです。
この形式は、ゴルフ会員権ではあまりなく、リゾート会員権特有のものだろうと思います。
このようなリゾート会員権の区分所有権に、
区分所有法(いわゆるマンション法)をそのまま適用してよいのかというと、
何となく違和感があり、法的な問題としては興味があります。
でも、俗世から離れるためのリゾート会員権ですから、
法律的なトラブルとは無縁であって欲しいものです。